
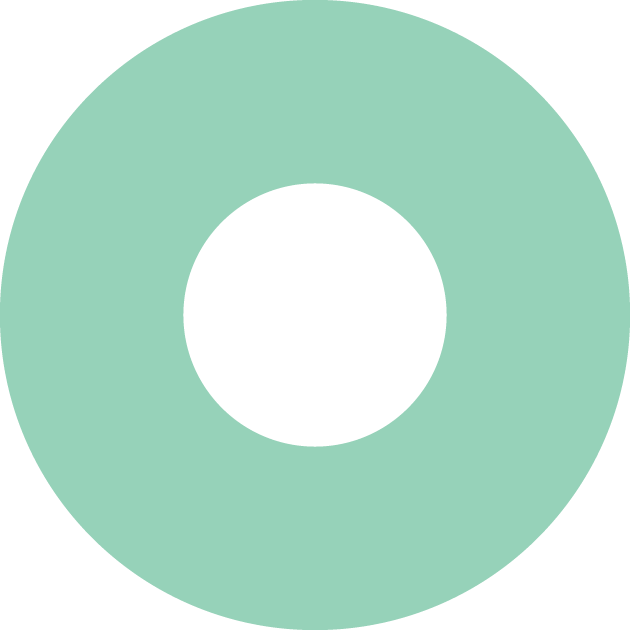
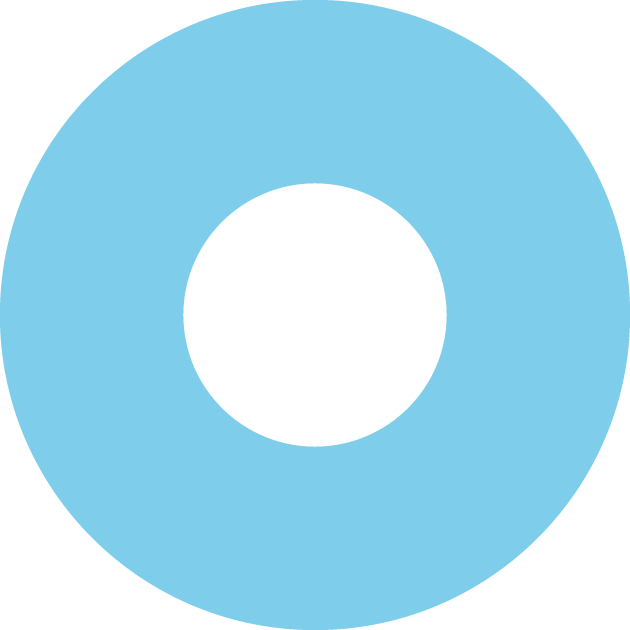
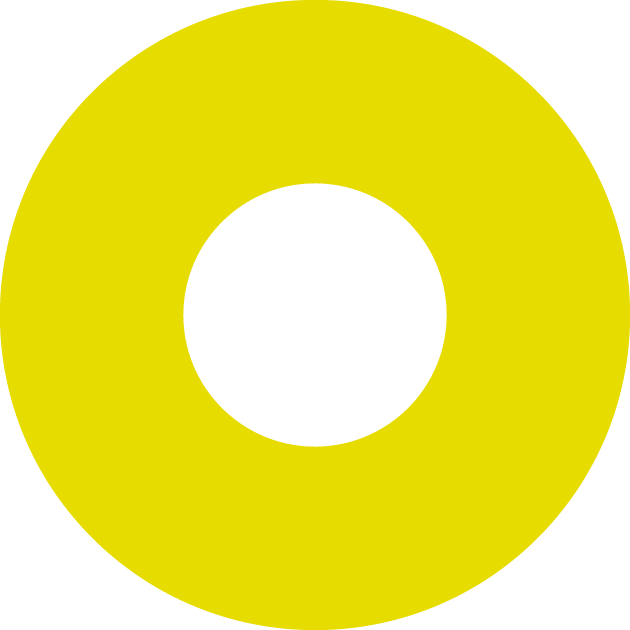
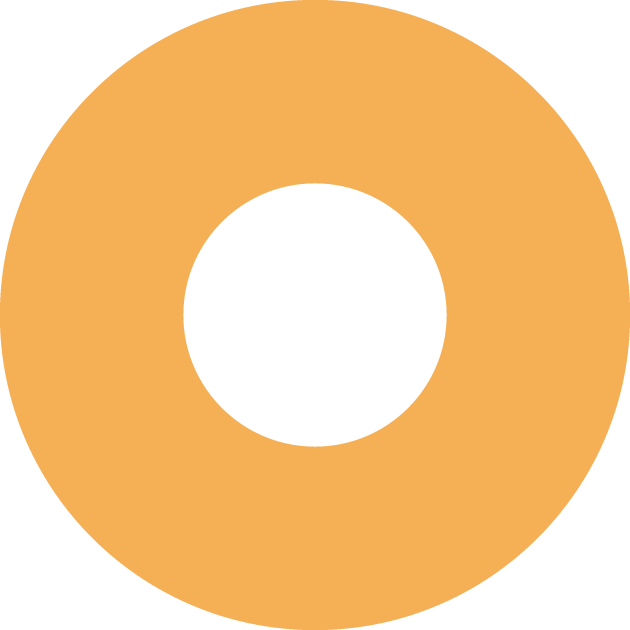

「もう行きたくない」と言われたらどうしよう……。そんな心配をよそに、息子が満面の笑みでスクールバスから降りてきました。「たのしかった!」初日の学校を終えた息子のこのひと言に、私は思わず胸をなでおろしました。今回息子が通っているのは、オーストラリア・クイーンズランド州にある私立の小学校。全校生徒に日本人はほとんどいない、本物の現地校です。
こうしたチャレンジの原点は、もっと小さなころにさかのぼります。彼が年中の頃から我が家ではホームステイの受け入れを始め、これまでにマレーシア、ハンガリー、タイ、香港から来た4人の留学生と、それぞれ3カ月〜半年ほど一緒に暮らしてきました。いずれも10歳ほど年の離れたお兄さん・お姉さんたち。異なる言語や文化の中での共同生活は、息子にとって「世界が家にある」ような体験だったと思います。そんな日々の積み重ねの中で、自然と外の世界への興味が芽生えていき、1年生の夏には、マレーシアのインターナショナルスクールに、2年生の夏にはオーストラリアの語学学校に2週間通うという経験を重ねてきました。
そして今年。いよいよ“本番”ともいえる、1ターム(約10週間)の現地校チャレンジ。しかも今回は、自分から「行きたい」と意思表示をしてくれたことが、何よりも大きな変化でした。早生まれであることや、現地の学期制度、英語のレベルも考慮し、学年をひとつ下げた2年生として編入。授業はすべて英語、日常会話もネイティブスピードという環境の中で、息子の奮闘が始まりました。
ことばの壁は、たしかにあります。最初の週は、「言っていることが全然わからない……」と、ぽつりとつぶやく姿もありました。戸惑いや不安もあったはず。それが、2週目の週末には「英語のしりとりをしよう!」と自ら提案してきてびっくり!「Mom! I’m hungry」と、家での会話にも英語が混じるようになり、「使えることば」が少しずつ彼の中に根を下ろし始めているのを感じます。
オーストラリアの学校生活ならではの魅力も、たくさん見つけたようです。午前中にある「スナックタイム」で友達とおやつを食べたり、本だけでなくボードゲームも楽しめる充実した図書館に夢中になったり。日本の学校とは違う、自由でのびのびとした時間を満喫しています。なかでもお気に入りは理科の授業。身近な素材を使った創作や実験が「すごくたのしい!」と、目を輝かせて話してくれました。
さらに、日本では当たり前だったことが、ここではちょっとした強みにもなっています。「日本の子は算数ができる!」と言われる通り、かけ算のスピードではクラスの誰にも負けず、“Math Hero”としてちょっとした人気者に。また、体育の授業ではリレーでもトップランナーだったそうです。言葉を超えて伝わる「得意なこと」は、どこにいても自信につながるのだと、改めて実感させられました。最近は、「ヘンボ(Handball)」というバウンスボールを使ったボールゲームにも夢中。休み時間には友だちと一緒に汗を流しながら遊び、すでに“仲間”と呼べる友人もできたようです。
次回は、息子が特に感動した「オーストラリアの理科の授業」の取り組みについてご紹介したいと思います。どうぞお楽しみに。
