
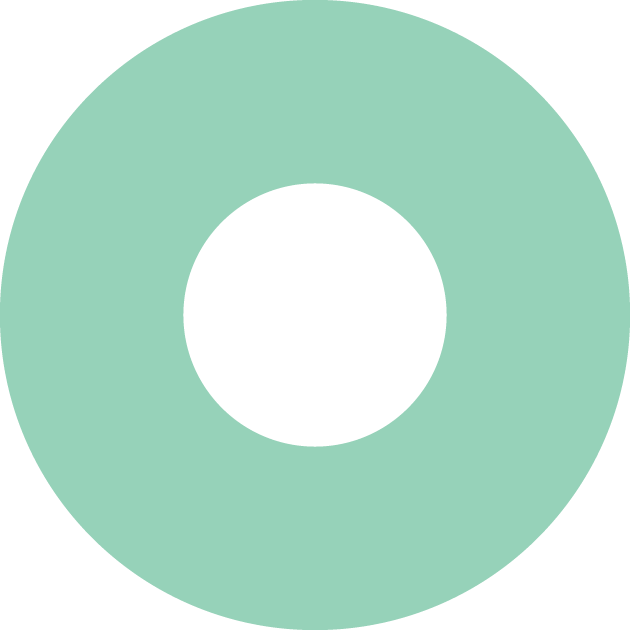
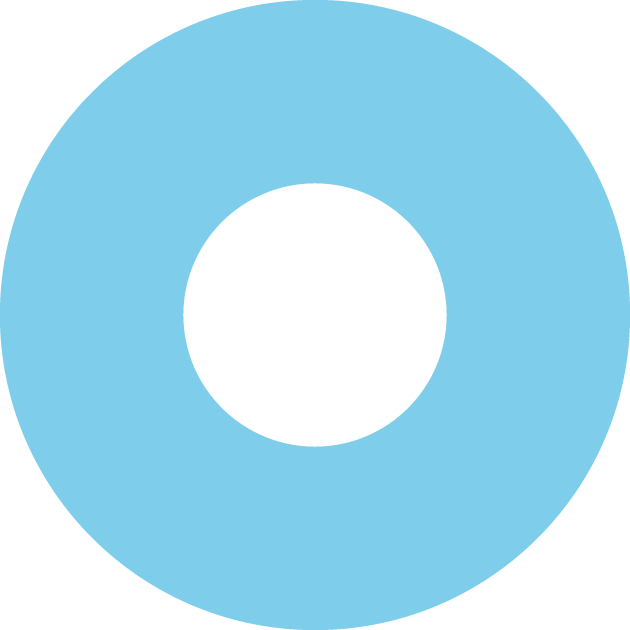
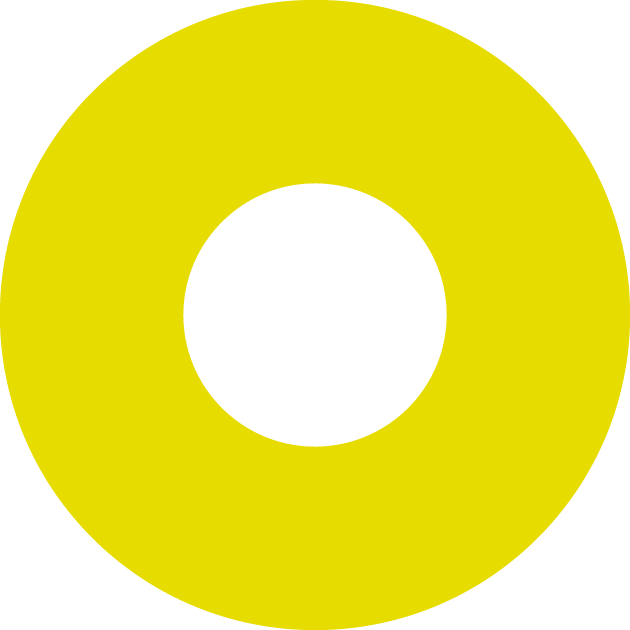
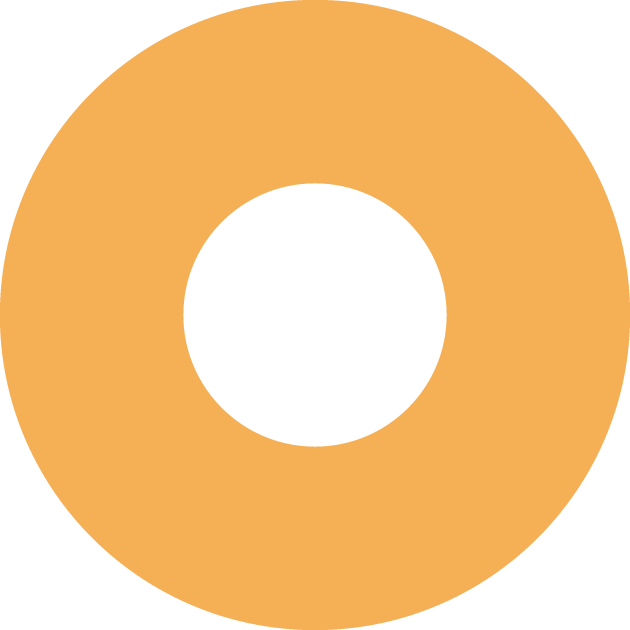

8歳の息子が挑戦している、オーストラリア現地校での1ターム留学。学校生活では、英語や友だちづくりだけではなく、学び方そのものにもこれまでになかった出会いがあります。息子が特に目を輝かせているのが「理科」の授業。日本の学校では中学や高校で習うようなテーマも、驚くほど楽しいアプローチで体験できるのです。今回は、その一部をご紹介します。
ある日のテーマは「月の満ち欠け」。まずは地球が描かれたプリントに、お弁当用のカップ皿を貼り付け、YouTube動画や模型を使って月の形の変化を学んだそうです。そしてここからが、本番。オレオを使った、おいしく楽しい実践の始まりです。まずは、太陽の位置を想像しながら、カップの中にオレオをセットします。スタートはクリームたっぷりの満月(full moon)から。そこから楊枝でクリームを削り、三日月や半月など、全部で8種類の月の形を作っていくのです。
彼はこの活動がよほど楽しかったようで、おやつの時間に食べずにとっておいた”月の満ち欠けオレオ”を、大事にタッパーに入れて持ち帰ってきてくれました。そして家に帰るなり、「ねぇ、月の形ってどんなのがあるか知ってる?」と得意気な様子。嬉しそうに、その日学んだ満ち欠けの仕組みを、作品を再現しながら説明してくれました。理科とおやつ、そしてアートがこんなにも自然に組み合わさる授業は、日本ではなかなか見かけることはありません。
また、ある日の授業テーマは、影(shadow)について。物体に対してどこから光を当てると影が大きくなったり小さくなったりするのかを、アート活動と組み合わせて実験したそうです。やり方はとてもシンプル。まず、アルミホイルで人の形を作り、その輪郭を画用紙に写して黒く塗り、影を書きます。仕上げにグルーガンで貼り付けたら、オリジナルの人形が完成。
これをライトでさまざまな角度や距離から照らし、影の大きさや形がどう変わるかを観察します。材料や手順はとても簡単ですが、自分で作った人間と影の大きさと、光を当てて映し出された影を比べるのがとても楽しいのだそう。
この授業以来、息子は家でも「影あそび」に夢中になりました。窓をスクリーン代わりにして影絵を映し出し、焦点距離が近いと影が大きく、遠いと小さくなることを何度も試しています。日本では、中学校で「実像・虚像」、「焦点距離」などを学んでいきますが、机上だけの学びではどうしても難しく感じがち。けれども、こうして遊びの延長で体感できると、「わかる!」がぐっと身近になります。
どちらの授業も、材料は家庭にあるもので簡単に再現ができるものばかりです。理科なのにアートで、おいしくて、遊び心があって……。こうした柔軟なアプローチによって、子どもたちの中に好奇心が広がり、「自分でも作ってみたい!」という創造のスイッチが押されていくのかもしれません。学びが机の上だけで終わらず、遊びの中に楽しく息づく——そんな授業を、LOUPEでももっと増やしていきたいと感じました。
